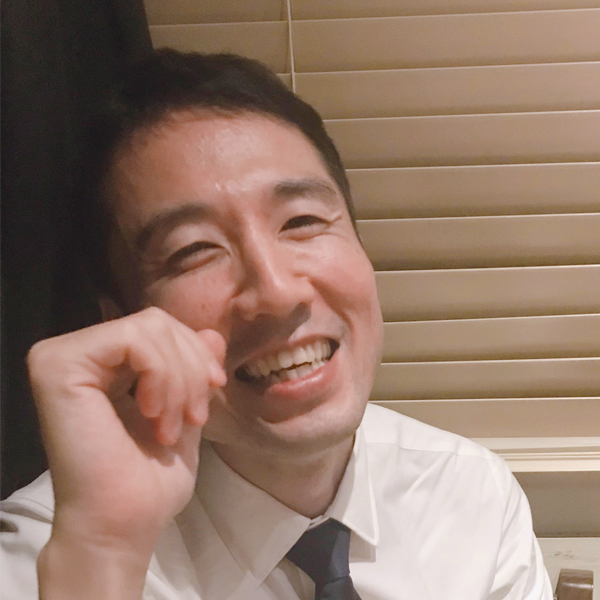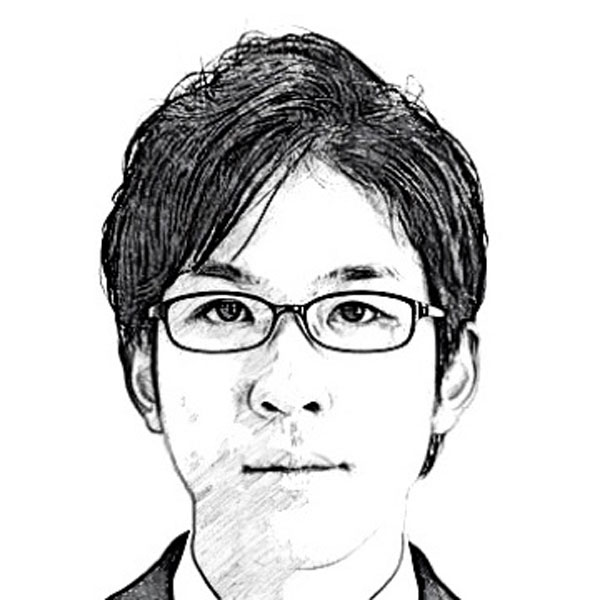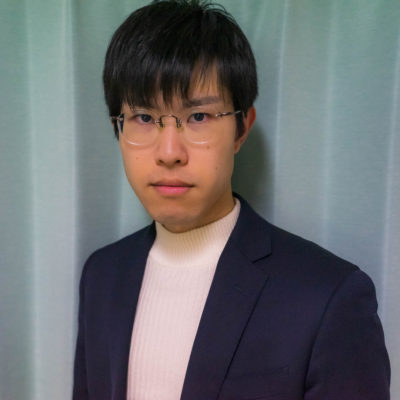あたりまえな食料の一つとして、
あたりまえに昆虫が利用される社会を目指して
日本はカイコ、イナゴ、ハチの幼虫などを日常的に食べる文化を持つ昆虫食先進国です。しかし、そんな日本でも昆虫を食べる研究についてはほとんど行われてきませんでした。それは多くの人にとっての昆虫は、利用するものではなく排除するものだったからかもしれません。昆虫には資源として大きな可能性が秘められており、今までのように排除ばかりしていてはもったいないのではないでしょうか。これからは昆虫を賢く利用していく時代、私たちは特に昆虫の食料利用の可能性を信じ、あたりまえな食料の一つとしてあたりまえに昆虫が利用される社会を目指していきます。
2018年7月
食用昆虫科学研究会 一同
私たちが目指す社会
例えばこんな社会を、できるだけ持続可能なかたちで実現していきます。
昆虫食が身近な社会はきっと今よりも豊かであると信じています。
より多様な美味しさ
食べられた記録がある昆虫の数は2100種を超え、その美味しさは多種多様です。サクラケムシの桜の香りと淡泊なうまみ、セミの肉肉しさ、バッタの爽やかな魚粉様の風味、他に代えられない美味しさが簡単に手に入ります。
より健康的な食生活
昆虫は一般的にタンパク質を多く含み、栄養が豊富な食材といえます。今はまだ研究が進んでいませんが、将来的には機能性成分も数多く発見されることも期待されます。私たちの健康的な食生活の維持を支えてくれています。
楽しい遊びの充実
自然の中に出かけて、自分で旬の昆虫を採集して食べる。そこには山菜採りやジビエに通じる楽しさがあります。春にはバッタ若虫、夏にはセミ、秋にはサクラケムシ、冬にはカミキリムシ。昆虫食を通じて、楽しい遊びが増えます。
経済の発展
欧米諸国を中心に世界の昆虫食関連市場は急成長しています。数年内には数百億円規模になるという試算もあります。昆虫プロテインバー、昆虫レストラン、フレッシュ昆虫…大きな昆虫食市場が経済発展に貢献しています。
研究会の役割
2011年、食用昆虫科学研究会は発足しました。昆虫食への注目が高まるにつれて同志も増え、2018年には15名を越すチームとなりました。私たちはチーム一丸となり、以下の2つの役割を担います。
昆虫食に関する情報発信
私たちは、より多くの人に昆虫食について考えるようになってもらうために、各種メディアを通じて昆虫食に関する正しい情報を発信していきます。また科学館や学校などでの各種イベント開催を通じて、みなさんとの昆虫食コミュニケーションを実践していきます。
互いに協力し合える場づくり
私たちは、昆虫食に興味を持つ人が集まり「自分のやりたい研究を仲間と実践する」場を目指します。自由研究や卒論、昆虫養殖ビジネス、昆虫食が救う食料問題、昆虫食アート、私たちは何でも興味があります。一緒に学び、チャレンジしていきましょう。
ロゴについて
Insect food glass
昆虫食による新しい食生活が見える虫メガネ
私たちが実現したいのは昆虫食による豊かな食生活と持続可能な社会です。私たちはその新しい世界を視る眼(Insect food glass)を持っています。このロゴは皆さまにその世界を少しでも覗いてもらいたいという想いを込めて、虫メガネと虫の持つ複眼をモチーフにしてつくりました。そしてロゴが連なることで形成されるネットワークは、本研究会を中心にした昆虫食文化を醸成することに共感した人々が集まるコミュニティを表現しています。
研究会概要
- 名称
- NPO法人食用昆虫科学研究会
(特定非営利活動法人食用昆虫科学研究会) - 設立
- 2011年5月
(2014年12月18日に法人格取得) - 役員
- 代表理事:佐伯真二郎
理事:水野壮、内山昭一、他2名
※役員はすべて無報酬 - 会員
- 17名
(2018年10月現在) - 電話番号
- 050-5436-9607
- 連絡先
- すべての会員が食用昆虫科学研究会とは別に本業を持ちながら、社会奉仕の一環として活動しております。
当会には専用オフィスもなく、お電話でのお問い合わせには対応ができません。
ご連絡につきましては、【お問い合わせページ】よりお願いいたします。